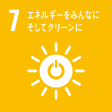ベネッセのマテリアリティ
さまざまな環境変化を踏まえ、2020年に発表した中期経営計画をブラッシュアップした変革事業計画を策定するにあたり、現状に即したマテリアリティの見直しを行いました。パーパスの実現に向けた3つの事業テーマとそれらを支える土台としてのESGの推進を新たなマテリアリティに設定しています。
見直しの背景
マテリアリティ制定から3年が経過し、社会環境の急激な変化、事業変革に伴い、各事業が向き合う社会課題にも大きな変化が生まれました。我々を取り巻くこれらのさまざまな周辺環境を踏まえ、2020年に発表した中期経営計画をブラッシュアップしたものとして変革事業計画を策定するにあたり、改めて現状に則したマテリアリティの見直しを進めるとともに、各マテリアリティに対してバックキャスティングを踏まえた具体的な目標を定め、サステナビリティと経営推進の統合をより図っていくことといたしました。
見直し(特定)プロセス
重視するポイントを3つに整理し、社内での議論および外部有識者との対話による示唆を踏まえ、経営レベルで議論を実施し、マテリアリティの見直しおよび目標の設定をいたしました。マテリアリティに関する目標の達成状況は、ステークホルダーの皆さまへ積極的に情報開示を行い、 責任ある対話を行ってまいります。
-
STEP 1
- 目指す企業グループの姿を再定義
- 企業哲学である「Benesse=よく生きる」とそれを実現するための共通価値としてのグループパーパス、2028年とその先の社会からのバックキャスティングにより、社会と当社の持続的発展に影響する社会の変化を踏まえ、変革事業計画の方向性を検討。変革事業計画が目指すことの第一番目として「人を軸にした社会課題の解決に圧倒的に取り組んでいる企業グループ」を設定。
-
STEP 2
- 重視するポイントの整理
-
グループパーパスおよび変革事業計画における目指す姿を実現するために、マテリアリティにおいて重視するポイントを整理。
- 企業哲学「Benesse=よく生きる」とグループパーパス
- 2028年とさらにその先の社会からのバックキャスティングを踏まえたライフステージごとの社会課題
- 社会の持続可能性に貢献するための企業への要請を踏まえた誠実な経営の実現
-
STEP 3
- マテリアリティの仮説
- STEP2で整理したライフステージごとの社会課題と社会からの企業への要請の重要度を精査し、マテリアリティを仮説。
-
STEP 4
- 経営レベルでの議論
- CEOが議長を務め執行役員が出席する経営会議や、常務執行役員が議長を務めCEOをはじめとした社内取締役および執行役員が出席するサステナビリティ推進委員会での議論を実施。
-
STEP 5
- ステークホルダーとの対話
- 仮説に基づき、有識者、NPOなどとの対話を実施し、外部観点からの当社グループへの期待や要請を確認し、検討プロセスに反映。
-
STEP 6
- 目標の設定
- マテリアリティに基づき、変革事業計画と連動した目標を設定。
-
STEP 7
- 取締役会による承認
- 経営会議などでの議論を経て、取締役会にて審議、承認。
ベネッセの価値創造プロセス
事業活動と社会活動を通じた人々の「Benesse=よく生きる」の実現、そして社会課題の解決につながる新たな価値を創造し続けることで、ベネッセグループと社会の持続的な成長を目指します。


マテリアリティ
子どもを取り巻く学び支援・社会人のキャリア開発支援・高齢者介護において重要な社会課題の解決に資する未来に向けた商品・サービスを提供してまいります。また、実現に向けた確固たる基盤を構築・保持し、社会からの信頼を得ながら、持続的成長を目指します。
多様化、多層化する学びに対する支援と意欲を高める教育の実現
- 人を軸にした課題
-
- 子育て環境の変化
- 教育機会の格差
- 学習意欲の低下
- 学ぶ目的や進路の多様化
- 教員の働き方改革
- 当社グループ資本
-
- テクノロジー/技術
- 社会関係資本(顧客基盤、学校・自治体、地域ネットワーク)
- 知的資本
- コミットメント
-
教育機会格差や多様性に寄り添える教育を社会に届け、未来を生き抜く力を持つ子どもを増やす
- 事業分野
-
- Kids&Family事業
- 校外教育事業
- 学校向け教育事業
- 具体的なアプローチ
-
- 圧倒的な顧客基盤をベースに、教育の専門知見とDXによって、多様なニーズに応える商品を拡充
- 既に多くの学校で使われているプラットフォームを基盤に、多様化する進路や教員の働き方変革を支援
- あらゆる子どもがアクセスしやすい教育の機会を提供
- 取り組み事例
・目指す姿
-
- 学校における評価+日常学習+校務をつなぐ新しい価値創造のスキーム、モデルづくり
- 2025年度「NextGIGA構想」を踏まえた進研ゼミ次世代化によるアクセシブルな学び
- 活動例
-
- 対応するSDGs目標
-
学びを通じた企業の持続的成長と個人のキャリア開発支援
- 人を軸にした課題
-
- 求められる資質、能力の変化
- 個人の自律的なキャリア開発
- 当社グループ資本
-
- 人的資本 (人財強化・要員増)
- 投資
- テクノロジー/技術
- 社会関係資本 (顧客基盤、行政・企業ネットワーク)
- 知的資本
- コミットメント
-
自分軸をもってキャリア・人生を歩む“個”の育成を通じ、企業が持続的に成長する力になる
- 事業分野
-
- 具体的なアプローチ
-
- 個人・法人・自治体利用が急増する「Udemy」で培ったネットワークなどを活かし、リスキリング市場をけん引
- 個人のリスキル・成長を通じたマッチング事業(採用・異動・就職・転職)を今後拡大
- 取り組み事例
・目指す姿
-
- 世界最大級の労働市場情報データベースを有するSkyHive社と資本業務を提携
- 日本の女性を中心とした就労支援Waris社グループイン
- 活動例
-
- 対応するSDGs目標
-
ご高齢者の“その方らしさ”の追求と介護をとりまく構造課題の解決
- 人を軸にした課題
-
- 要介護高齢者の増加
- 介護人財の不足
- 介護業界のDX化の遅れ
- 当社グループ資本
-
- 人的資本(専門人財)
- テクノロジー/技術
- 知的資本(ノウハウ)
- 社会関係資本(介護人財との多面的な繋がり)
- コミットメント
-
高齢者のQOLを高めながら、ロールモデルとなる介護人財を増やし、介護を「選ばれる仕事」に
- 事業分野
-
- 具体的なアプローチ
-
- 高度な専門性を持つ優れた介護人財の育成を、自社として体系だてて推進するとともに、得られた知見を積極的に社会に還元
- “人”とテクノロジーを掛け合わせて暗黙知を可視化
- 介護人財不足解消に向けた事業展開
- 取り組み事例
・目指す姿
-
- 高齢者のQOL向上に寄与する専門人財(「マジ神」)認定制度とその育成体系を導入
(25年度までにのべ600名以上輩出)
- 介護福祉士の資格取得支援
- AI技術を取り入れたベネッセセンシングホームの拡大(24年度までに全拠点)
- 活動例
-
- 対応するSDGs目標
-
- 当社方針
-
ラーニングカルチャーをベースに個人の自律的な成長支援を目指す
会社はその機会を提供する
- コミットメント
-
事業を通して社会課題の解決をけん引する多様な人財の輩出
- 具体的な
アプローチ・目標
-
- デジタルおよび変革に必要なキーポジションと専門性の可視化・育成を行い、2025年度のデジタル人財充足率は85%以上を目指す
- 経験や年齢、ジェンダーなどダイバーシティを推進し、2025年度女性業務執行役員1名以上・女性管理職比率30%以上にする
- エンゲージメント向上へのキャリア開発支援などの推進 : エンゲージメントスコア目標A
- 活動例
-
- 対応するSDGs目標
-
- 当社方針
-
企業理念・パーパスを実現するうえでも、「環境」を経営の重点課題の1つと位置付け、当社グループの事業特性に合わせて積極的に推進する
- コミットメント
-
未来を生きる子どもたちが、安心して住み続けることのできる地球環境の保全
- 具体的な
アプローチ・目標
-
GHG排出量削減中長期目標の設定およびSBTi認証の取得
- ベネッセグループ :スコープ1・2 (1.5°C目標) 2030年42.4% 2041年100%
- ベネッセコーポレーション :スコープ1・2 (1.5°C目標) 2030年52.8%(※) 2041年100% 2050年100%(※) スコープ3 (2°C目標) 2030年14.8%(※) 2050年39.4%(※)
(※)はSBTi認定済み
- 活動例
-
- 対応するSDGs目標
-
- 当社方針
-
事業会社各社による自律的な成長と、経営監督機能のさらなる維持・向上を図るべく、経営体制の構築、運用に取り組む
- コミットメント
-
理念・パーパスのもと誠実で健全な経営をグループ全体で推進するとともに、事業を通した顧客価値を最大化
- 具体的な
アプローチ・目標
-
- ベネッセグループパーパス・行動指針に基づく、各社行動基準を全社制定
(新規グループイン会社は1年以内に実施)
- 継続的にPDCAを用いたコンプライアンス活動を全事業会社において実施
- セキュリティーデーの継続、定期的なセキュリティ研修の受講など、情報セキュリティのさらなる徹底
- 人権デュー・デリジェンスや啓発活動を通した人権に関する取り組みの向上
- 活動例
-
- 対応するSDGs目標
-